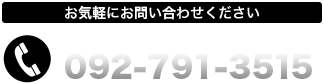拳を固めてサワディカップ24-3
 3月2日、9:00起床。WOW CAFEの隣の食堂で50B(200円)のクイッティアオの朝食。
3月2日、9:00起床。WOW CAFEの隣の食堂で50B(200円)のクイッティアオの朝食。
部屋でのんびりくつろいだ後、バルコニーに出て、プールに日が差し始めたのを確認してから、1時間ばかり泳いでいつもの日光浴。うとうとしていると、教え子のアヌチャイ・ドンスアから電話。ナコンサワンで行われたジョシア・ルムンヤ(ウガンダ)との試合に判定で勝ったとの報告。0勝4敗の相手にはもっと簡単にノックアウトしてほしかったが。
15:00、タクシーを手配してサーサクン・ジムへ。今日はフン君につきっきりで特訓した。3月27日に試合を控えているフン君に長いジャブを徹底的に磨き、そこから放たれる右ストレート、続く左ボディを何度も何度も繰り返させる。力任せのボクシングでデビュー戦を飾ったフン君だが、次は技術でKOする醍醐味を味わわせてあげたい。
テーマはまず、「見る」こと。多くのボクサーは「見る」を勘違いしていると思う。
タイミングや的を「見て」パンチを打ち出す。
当たる瞬間を「見つめる」。
当たったのを「見届ける」
ここまで見て初めて「見た」といえると思って指導してきた。ここまでやってこそ会心のパンチが炸裂するのだと信じている。
フォームや目の位置、目の動きを厳しく指導して、ミット打ちに入る。元々、練習熱心なフン君は強いパンチを持っている。その強打をどこに、どのタイミングで炸裂させるかで倒せる選手とそうでない選手に分かれてしまう。天才肌の強打者、アヌチャイもこの当て勘がよくないばかりに、KO勝ちすることができずにいる。
重心と目の動き、これが少しでも狂うと初めからやり直し。地味な練習だが、フン君も泣きを入れずに真剣な表情で練習についてくる。気が付けばマンツーマンの指導は3時間にも及んでいた。
シャワーを浴び、着替えを済ませると、サイトーンから電話。
「ケン、タイに来ているんだろう?これからうちの選手が試合するから見に来てよ」
急いでタクシーを呼び、ワールド・サイアム・スタジアムへ。
インド人が主催するローカル興行だった。主役の赤コーナー側はすべてインドやパキスタンの選手で青コーナーはすべてタイ人。接待のような斬られ役のような、とんでもない試合が延々と続いた。階級も2.3階級はが違うんじゃないかというほどの対格差。羽振りのいいインド人主催者や客を喜ばせるためだけに、無気力なタイ人がタイのリングでカネのためだけに、次々と倒されていく。サイトーンの選手ももちろんやられた。
昔、日本にやって来ては、不甲斐ない試合をして、KO負けした後、ヘラヘラしている咬ませ犬のようなタイ人を見て「ふざけるな、ボクシングを馬鹿にするんじゃない」と憤慨していた時期があった。
以前、チュワタナジムへ選手を連れて合宿をしたとき、いつも日本でだらしなくやられていたタイ人がスパーリングで恐ろしく強かった。さらに、ムエタイのチャンピオンではあるが、まだ国際式ボクシングに転向していなかったジョムトーン・チュワタナと手合わせしたが手も足も出なかった。合宿のスケジュールはまだ数日残っていたが、
「こんなに力の差があったんじゃあ、勉強にさえならないですよ。もう帰りたいです」
泣きが入った選手にかける言葉さえなかった。負け犬だと思っていたタイ人たちは、ふざけてなんかいなかった。家族のために体を張って外貨を稼いで帰ってくる。壊されないように帰ってくる。そうして必死に家族を養っている。映画のスタントマンや、名もない斬られ役の、時代劇の大部屋役者を思い出した。日本ではボクシングじゃなくても食べていける。ほとんどの日本人ボクサーはほかに仕事を持っている。タイ人ボクサーはこれで食べていくしか他に道がないのだ。中途半端に勝ってしまっては、もう外貨を稼げる海外からお声がかからなくなってしまう。彼らは自分の立場を十分すぎるほどわかっているからこそのあの試合っぷりだったのだと分かった。一体どちらがよりプロフェッショナルだといえるのか、わからなくなってしまった。
情けないが荷物をまとめ、逃げ帰ろうとしたその時、ふと携帯電話のニュースを見ると、
「長谷川穂積、1ラウンドKOでWBC世界バンタム級タイトル防衛」
の文字が飛び込んできた。
荷物をまとめる手を止めて、
「おい、逃げるのはやめよう。これを見ろ。日本人がしっかり世界に通用しているじゃないか。やるだけやって胸を張って帰ろう。明日からもまたひどい目に遭うだろうけど、その中で自分たちが何かを勉強して一つでもいい、何か土産を持って帰ろう」
そう言って最終日まで殴られ続けた2週間を思い出した。
そんなタイ人たちが、今度は自国でカネのために倒されている。ひとりひとりのバックボーンはわからないが、もう彼らのことをだらしないとは思わなかった。
すべての試合が終わった後、サイトーンと再会の握手をして、短い会話をしただけでさっさと会場を後にした。