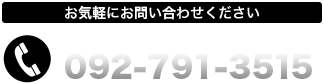拳を固めてサワディカップ25-4
 5月20日、この日は予定がないので、昼前までホテルの部屋でゴロゴロした後、MBKに買い物に行き、フードコートで朝食兼昼食。タイマッサージをはしごして、コンディションは100%に回復した。夕方から青島氏の自宅にてビールを飲みながら夕食をごちそうになる。21日と22日にシンマナサックジムで行われる日本人選手の試合のことや、最近のボクシング事情などを話し合いながらの楽しい夜だった。
5月20日、この日は予定がないので、昼前までホテルの部屋でゴロゴロした後、MBKに買い物に行き、フードコートで朝食兼昼食。タイマッサージをはしごして、コンディションは100%に回復した。夕方から青島氏の自宅にてビールを飲みながら夕食をごちそうになる。21日と22日にシンマナサックジムで行われる日本人選手の試合のことや、最近のボクシング事情などを話し合いながらの楽しい夜だった。
5月21日、9:00起床。近所の屋台でカオマンガイの朝食、40B(160円)。11:00からチャトチャック・ウイークエンドマーケットへ行き、妻にスニーカーをプレゼント。昨日MBKで買い忘れたお土産を買いこんでホテルに戻る。今日の気温は39℃。冷たいシャワーをいくら浴びても噴き出す汗がしばらく止まらなかった。
15:00.支度をしてサーサクン・ジムへ。疲労が抜けたヨードモンコンを2時間、マンツーマンでの指導。思い切って休養を取らせてよかった。動きに切れが戻り、パンチもずいぶん鋭くなった。休養中にウエイトが若干増えたのが心配だが、次戦の重要さは彼もよくわかっているだろう。ヨードモンコン陣営の人間でありながら、冷静に判断すると、今度の比嘉戦はかなり分が悪いことはわかっている。世界ランカー同士の試合とは言いながら、ヨードモンコンは2階級下のクラスだし場所も東京。世界王座への返り咲きを狙う比嘉がヨードモンコンを踏み台と考えているのは想像に難くない。
昔からそうだった。日本の選手を指導していた時も、地方ジムの悲しさから、有利な条件で大舞台に立ったことがない。不利な条件の中、詰めかけた観客のほぼ全員がこちらがやられるのを、今か今かと心待ちにしているのを肌で感じながら、持てる力の最後の一滴を絞り出すようにして勝利への細い糸にしがみついていった20年間があった。そうして勝ったり負けたりを繰り返してきた。あの20年は何物にも代えられない宝物だと今、改めて思う。世界中が「絶対に無理だ」と、どんなに酷評しても、勝利を固く信じて前を向いていられるのは間違いなくあの20年間のおかげだった。
下手なタイ語と英語を織り交ぜてそういう意味のことを、時間をかけてヨードモンコンに説明する。一瞬たりともこちらから目をそらすことなく話を聞いていたヨードモンコンが、
「ラオ トン タム ダイ、ラオ トン タム ダイ(我々はやるしかない)」と、
2回繰り返した。つぶやくような小さな声だったが、決意のこもった力強い声だった。
続くタマノーン、パンヤとのミット撃ちが終わったころには、もう汗だく。拭いても吹いても汗が止まらない。右のこめかみに刺すような鋭い痛みがある。いやに視界が上下に狭い。熱中症だとすぐに気づいた。扇風機の前で少し休んだ後、30分水シャワーを浴び続けた。体の熱が取れ、やっと視界が開けてきたところで、ビーさんから電話。
「練習終わりましたか? これから食事に行きましょう。チャッチャイにはもう伝えてあります。これからジムに向かいます」
30分ほどで到着したビーさんの車に、チャッチャイ、リン、妻の4人で乗り込み、車で10分走ったところにあるレストラン、Bo Nguen Restaurant Klong4へ到着。名前からして、ベトナム料理店かと思いきや、メニューにはタイ料理のみがずらりと並んでいる。
熱中症で干からびた体に流し込むビールは、違法薬物じゃないかというくらい心地よかった。テーブルに並べられた豪華なタイ料理を楽しみながら、とりとめのない話は尽きない。スマホを最新機種に変えたんだというチャッチャイが上機嫌で写真を撮りまくる。確かに、プロが撮ったんじゃないかというくらい美しい写真だった。
唐突に会計を済ませたチャッチャイとリンが、先に帰るから、と席を立った。
残された3人で話をしていると、ビーさんが照れくさそうな顔で、
「コロナの影響でジムの運営はガタガタです。練習生は誰ひとりジムに来ないから、毎日何もせずに時間だけが過ぎていきます。実は、家とジムを売却して、妻の実家に引っ込んでしまおうかと考えているんです」
「カネで済む話ではなくて?」
「はい。カネで維持するだけでは、カネを捨てているのと同じです。指導をしたいんです。これまで私はコーチをやってきたんです」
何と声をかけていいかわからなかった。海外渡航や飲食事業が解禁になったとはいえ、コロナ禍はまだまだ日常にしっかりと根を張っている。もう少し踏ん張れば大丈夫ですよ、なんて軽々しいことはとても言えなかった。彼はもう充分に耐えてきたはずだ。コロナ禍で渡航禁止の時もテレビ電話をかけてきては、「ケンさん、元気にしてますか?仕事頑張って。体に気を付けるんですよ」と、自分よりも先に、周りを心配するような彼が、今こんなことを言い出した。
ここまでの切実な話には、思い付きのアイデアや当座の工面など、付け焼刃の軽口をたたく気には到底なれない。いくら考えても、きれいな夜空を見上げても何一つ言葉が出てこない。目の前のビールグラスは汗をかき尽くしてすっかりぬるくなっている。
「前を向いていてください」
そう答えるのが精いっぱいだった。
この後、深夜便で帰国する妻をビーさんがドンムアン空港へ送ってくれた。妻をチェックイン・カウンターまで送り届けた後、もう少しビーさんと一緒にいようかと思ったが、一晩かかっても彼に何もできないことはわかっていた。
笑顔で「ありがとう、またね」と手を振るしかなかった。