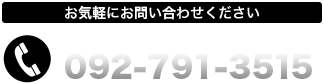拳を固めてサワディカップ26-3
 第1ラウンドのゴングが鳴った。
第1ラウンドのゴングが鳴った。
想像していた通り、挑戦者、田中の闘志が素晴らしい。上体をエネルギッシュに振りながら、王者パンヤーに肉薄してくる。練習で何度も繰り返した強い左ジャブを寸断なく打つが、巧みなパーリングと絶妙な距離の詰め方で、委細構わず突進してくる。
ホームのリングとはいえ、まずい流れだなと思っていると、勢いづいた田中が無防備に右フックを強振したタイミングで、パンヤーの右ショートストレートがカウンターとなって挑戦者のアゴに炸裂。続く返しの左フックで田中はあっけなくキャンバスに腰から崩れ落ちた。
カウント8で立ち上がった挑戦者はゴングに救われる。
2ラウンド、ダメージの残る田中に対して、KOを焦るパンヤーは的確にパンチを決められない。
3ラウンドはまたもやビッグラウンドになった。冷静さを取り戻したパンヤーに「よく見て、相手の打ち終わりにカウンターを決めろ」と指示を出すと、ドンピシャのタイミングでワンツーがヒット。田中の足元が大きく揺れる。
「パイ ルーイ(勝負に行け)!」
リングサイドからそう叫ぶと、パンヤーは意を決して怒涛のラッシュ。朦朧とする挑戦者を、1分以上打ちまくった。挑戦者コーナーのセコンドが肩から下げたタオルを投げ込もうと握りしめたのが見えた。
4.5ラウンドを驚異的なタフネスと精神力でしのいだ田中に、第6ラウンド、パンヤーが猛然と襲い掛かる。何度もぐらつきながらも挑戦者はパンチを打ち返す。防戦一方になってしまうとレフェリーが試合を止めてしまうのを充分にわかっているのだろう。見事な執念だと思った。しかし、限界に近付いているのか、その打ち返すパンチに力がなくなってきた。
7ラウンド終了後のインターバルに相手のコーナーに目をやった。次の回で最後だ、勝負をかけてこいと指示しているのが見えた。
「パンヤー、次の回、相手は勝負に来る。落ち着いてよく見ろ。必ず雑な右を振ってくる。いいか、冷静にカウンターを打ち抜いてこい。このラウンドで終わらせろ」
パンヤーの目つきが変わった。
案の定、挑戦者は最後の力を振り絞って猛ラッシュをかけてきた。歯を食いしばって狂ったようにパンチを打ち出すその姿は美しいとまで感じた。
「モーンクワー ドゥー チャンワー(右に回ってよく見ろ)」
そう叫んだ直後、ロープ際で田中が全身全霊の右を振るったとき、パンヤーの右ショートが挑戦者を支えていた最後の一本の糸を断ち切った。
挑戦者のヒザが怪しく震え、青コーナーのセコンドがタオルを振りながらリング上に駆け上がってきたその瞬間、レフェリーが瀕死の挑戦者を抱きかかえた。8ラウンド2分11秒TKO、前回苦戦した田中を見事、返り討ちにしてWBC(世界ボクシング評議会)ミニマム級タイトル4度目の防衛に成功した。
鮮やかな完勝劇に控室のテント内はお祭り騒ぎだった。テレビやボクシング雑誌のインタビューが延々と続く中、テントの外では身重の奥さんが心配そうにこちらを覗いている。
「おめでとう、彼はよくやったよ。これで生まれてくる子供が世界王者の子供として産まれてくることができるね」
そう言うと、大きなおなかをさすりながら泣き出した。
ひと通りインタビューが終わったところでパンヤーとスポーツドリンクで乾杯した。
「どうでしたか?ぼくは力強くなったでしょう?」
「おめでとう。すっかりたくましくなったね。以前、線が細いといったのは撤回するよ」
グローブとバンデージをはがし、拳に異常がないことを確かめたところで私の今回の仕事は終わった。
すっかり陽も傾いてきた。チャッチャイたちはこのままラムルッカに帰るという。今日は青島氏とパタヤのホテルに泊まる予定なので、一応フン君も誘ってみると、
「僕もパタヤに泊まりたいです。一緒に連れて行ってください。みんなで乾杯しましょう」
急遽、フン君の分のホテルも予約を追加し、三人で祝勝会をすることになった。
青島氏の運転で2時間かけて、ウォンガマット・リゾート・レジデンスへ。50畳はあろうかという異常に広い部屋にチェックインすると、すぐにウォーキングストリート沿いのバンブー・バーへ。
ウエイトレスは全員小太りの中年女性ばかりだったが、そんなことは気にせずに勝利の美酒に酔いしれた。ディスコ・サウンドが爆音で流れるオープンテラスで、3人ともビールをあおり、ウィスキーソーダで何度も乾杯し、我を忘れて踊り狂った。後で聞いたところによると、フン君はトイレに行った際に、椅子に置いていた財布から、ウェイトレスに250オーストラリア・ドル(25000円)を盗まれたそうだ。浮かれすぎなんだよ。みんなで腹を抱えて大爆笑した。
初めて訪れたパタヤビーチは、噂に聞いていたほどいい街じゃなかった。街は汚いし、どこか垢抜けない。オネーチャンたちも隙あらばホテルについてこようとするし、フン君に至ってはスリにまで遭っている。
でも、そんなことはどうでもよかった。生ぬるい潮風を浴びながら、このまま時間が止まってしまえばいい、ずっとここでこうしていたい、そう思ってしまうほど、うれし過ぎる夜だった。